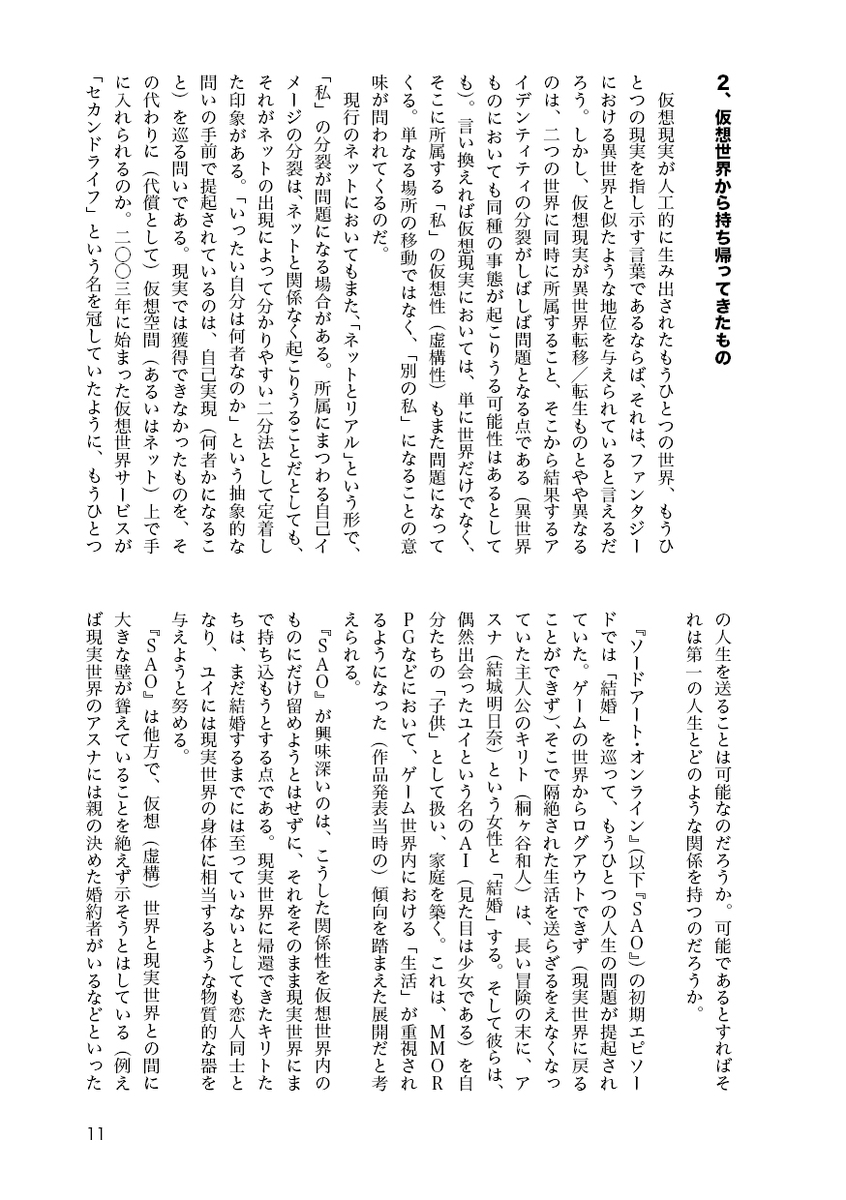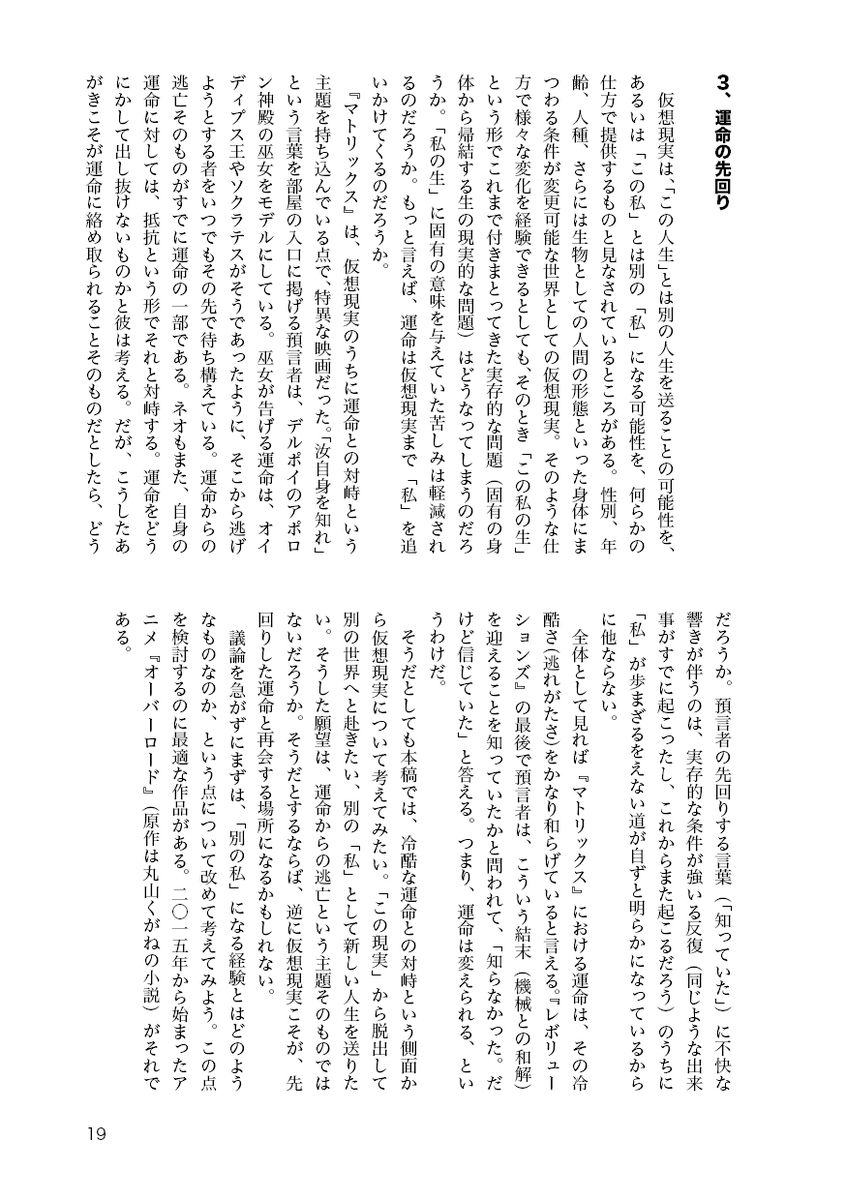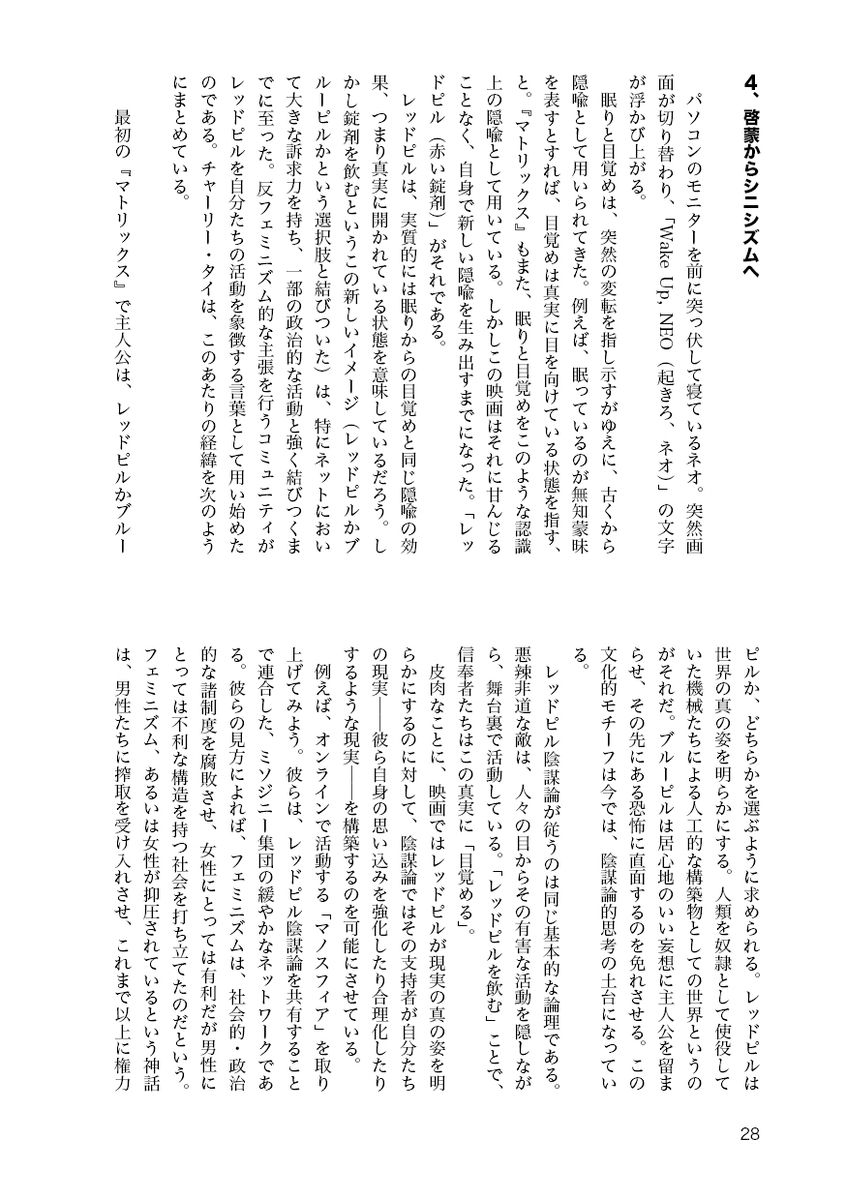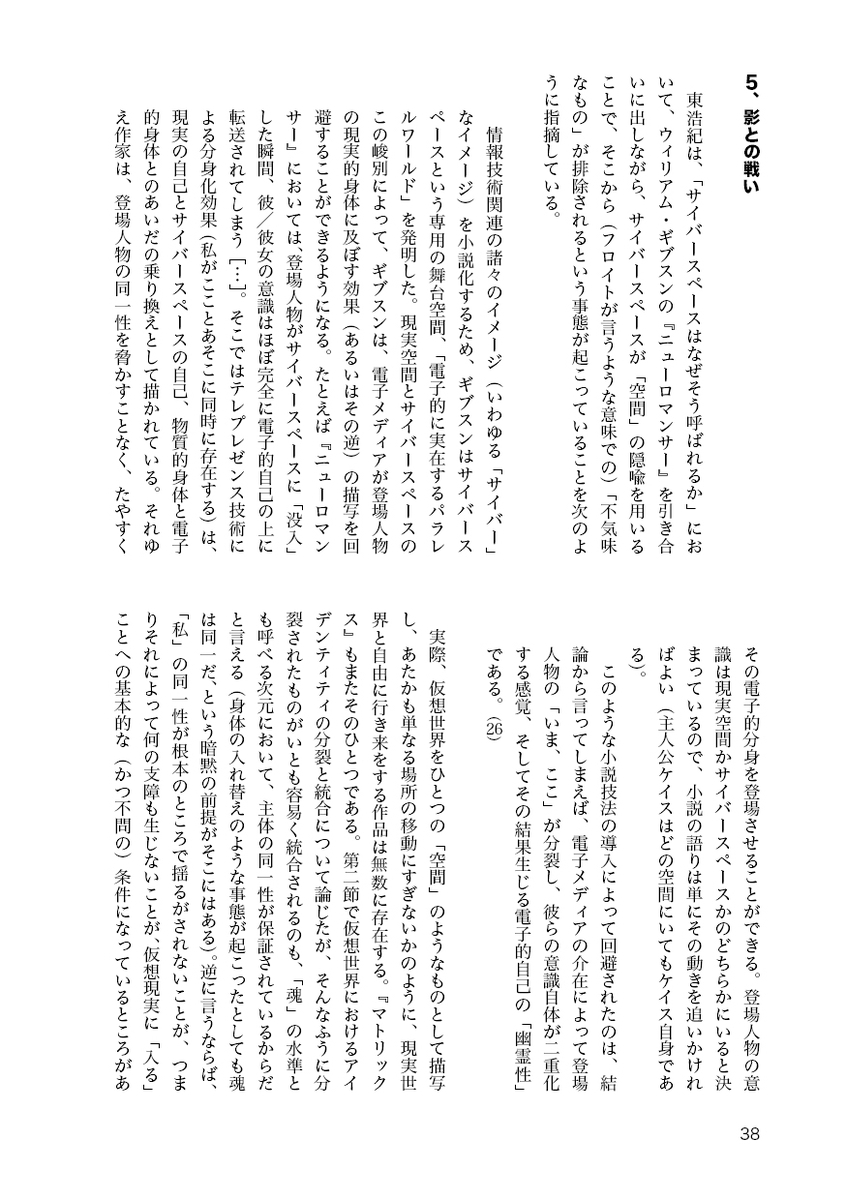原案・総監督:手塚治虫、チーフディレクター:杉山卓、制作:虫プロダクション、全52話
虫プロのテレビアニメ・シリーズとしては、『鉄腕アトム』(1963-66)に続く二作目。『W3』の放送が開始されたのと同じ年には、『ジャングル大帝』(1965-66)もまた始まっている。つまり、1965年から66年にかけて虫プロは、テレビアニメのシリーズを三つも手掛けていたことになる。
手塚治虫のマンガ版が存在するが、これは原作ではない。アニメの企画がまず先にあり、それと歩を合わせる形でマンガのほうも描かれた*1。つまり、『W3』のマンガとアニメは、基本的な設定を同じくするだけの別作品である。アニメ版の物語形式は、マンガ版のようなひと続きのものではなく、一話完結。そのため、アニメの『W3』は、大きな水準で物語が進行することはほとんどなく、(すでに『鉄腕アトム』がそうなっていたように)ある種のパターンを形成・反復していくことになる。
戦争を始めとした争いごとをいつまでたってもやめようとしない地球人を滅ぼすべきか否か、その決議のための調査任務を銀河連盟から課された「ワンダースリー」(三人の宇宙人)という大枠の物語設定がまず存在する。この宇宙人たちと交流を持つことになるのが主人公の少年・星真一である。ワンダースリーはそれぞれウサギ、カモ、馬という動物に変身し、真一の家に飼われる形で調査を続ける。
『W3』の設定で興味深いのは、真一の他にもうひとりの主人公を据え置いた点だ。真一の兄・光一がそれであり、この点からするならば、『W3』は二つの物語をひとつに統合した作品だと言える。光一は、表立っては駆け出しのマンガ家として振る舞っているが、実際は秘密諜報機関フェニックスのエージェントで、様々な悪の組織と戦うことを使命としている。60年代は『007』の映画シリーズが始まった時期であり、そうした当時のスパイブームに追従する形で、「諜報」というモチーフが二重に(ワンダースリーとフェニックス)取り入れられたのだと想像される。
マンガ版では、こうした二層構造が、グローバル(世界征服を主目的に掲げるような暴力的な国家や組織との国際的な対決)とローカル(村の地主に集中する利権とそこから生じる支配関係に対する闘争)という二つの領域における悪との戦いという形で、上手く機能している。だがアニメのほうでは、一話完結という制約が大きいためか、こうした複雑な構造は、単純な勧善懲悪の物語へと還元されてしまっている。たいていは、各エピソードにおいて、「悪」を代表する人物なり組織なりが登場し、真一、光一、ワンダースリーのそれぞれが一致協力する形で、そうした悪者たちと戦い、勝利するという物語のパターンが繰り返されるだけになっている。
別の観点からすれば、真一と光一の兄弟は、子供と大人の領域の区分をそれぞれ代表していると考えられる。つまり、子供は、その無力さゆえに、大人たちの関係性のうちに参入できないとしても、何か別の媒介の助け(『W3』で言えば宇宙人たちの不思議な能力)を借りることによって、大人の世界に影響力を行使できる。この当時のマンガやアニメにはこうした類型(大まかに言えば「少年探偵」というキャラクター)が散見されるが、この水準から言うならば、真一のやっていることはほとんどアトムと変わらなくなる。つまり、真一と光一という二人の主人公がいる必然性がほとんどなくなってくるのだ。
もちろん、50話以上も話数があるので、こうしたパターンに当てはまらないエピソードもたくさんある。悪者との戦いも極めて牧歌的な形で描かれているので(人が死ぬようなことはほとんどない)、全体的にユーモラスな印象を与える作品になっている。60年代のノリと(ギャグ)センスが随所に見出され、特にカモのプッコと馬のノッコとの間には掛け合い漫才的なやり取りがしばしばなされる(二人が「すいません」という言葉を何度も繰り返すエピソードがあるが(第29話「消された一日」)、これはおそらく林家三平を意識したものだろう)。
早口でまくし立てるプッコ(声の担当は近石真介)の長口舌はひとつの見どころで、おそらくアドリブもたくさん入っているのではないかと想像されるが、口パクのアニメーションにほとんどこだわらない形で、長い台詞が滔々と読み上げられる。いつ頃から口パクと台詞とをきっちり合わせるようになったのか分からないが、60年代から70年代にかけてのテレビアニメは、この点に関して、かなり緩やかな印象がある。
変わった演出ということで言えば、第36話「ジャングルのちかい」という残留日本兵を題材にしたエピソードにおいて、学徒出陣などの太平洋戦争時の実写映像が用いられるシーンがある。60年代から70年代のテレビアニメでは、この種の実写映像やスチール写真を部分的に用いた演出がいくつか見られるが、そうした事例の中でもこれはかなり初期のものであるだろう。
全般的にこの頃のテレビアニメは、ひとつのエピソードに多くの時間や人を費やせないという金銭的な制約のゆえに、それに適合した表現が様々に模索・開発されていた時期だった。虫プロはその代表的な制作会社であるが、『鉄腕アトム』の初期に見出されたようなぎこちなさは、かなり低減した印象を受ける。これは、つまり、テレビアニメ独自の見せ方が(ある程度)定着し出したということであり、例えば派手なアクションを見せなければならないときに人物の動きが制限されたものだとしても、素早いカット割りやカメラワーク(特にトラックアップ/バック)の多用によって、それなりに迫力のあるシーンが生み出される結果になっている。
*
作品内容に話を戻せば、『W3』において大人の世界が示されるとしても、それは、世界征服を企む悪の組織との戦いといった極めて空想的な形においてである。「悪」の問題はその種の闘争のうちに単純化され、もっと複雑な形で問いただされるべき悪、例えば「必要悪」のような考えすら問われることはない。唯一の例外は、人間が存在することそのものが悪の源泉なのかもしれないという初発の設定であるが、この点もまた、未来への希望(人間同士の争いを人類はいつか克服できるかもしれない)という形で先送りされ、徹底的に問われることはない。
1962年にキューバ危機があり、ベトナム戦争が継続していた60年代半ばの状況がこの作品に影響を与えていたとしても、(『007』のような)スパイものが題材としていた冷戦下の具体的な国際関係が『W3』において俎上に載せられることはない。これは単に国際的な状況に対する鈍感さを示しているというよりも、自国の正当性の自己弁護に汲々とせざるをえない敗戦国日本の苦難があったからだと考えられる。この点で、銀河連盟という上位組織に対して人類の健全さを証明するという基本的な設定は、アメリカを始めとした西側諸国(あるいは国連)に対する日本の立場を必然的に想起させる。
アニメ版『W3』の最終回は、マンガの終わり方に近く、反陽子爆弾を実際に用いようとするワンダースリーに対してフェニックス側が戦いを挑むという内容になっている。それまで仲間だと思っていたワンダースリーが人類の敵だと分かったときに、真一は彼らに向かって罵倒の言葉を浴びせかけるが、これは、広島と長崎に原爆を落としたアメリカに向けられた言葉というふうに捉えることもできるだろう。実際のところ、冷戦下の(核戦争の)危機は、日本にとっては、再びその国土に強力な爆弾が落とされるかもしれないという、具体的なリアリティの下で体感されていたように思える。